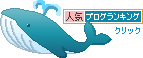それならぼくは、番い目にでもなろうか。ぼくが箍にさえなってしまえば、きみのその不安はすべてこのぼくが受けとめてしまえる。
恭一はとても安易な理由で、茜ちゃんをひとり残して逝った。
ある時期、茜ちゃんはとても不安定だった。幼馴染ではあったけれど、恋人ではなかったとおもう。ただ、子どもの頃からずっと兄妹同然に育ってきたから、そんじょそこらのぽっと出カップルなんかとは比べ物にならない信頼関係が築かれていた。関係性についてはわたしも同様であったはずだけれど、わたしは恭一よりも年の近い茜ちゃんをお手本に選んだ。それは茜ちゃんが、拠りどころとしてのお手本に恭一を据えていたからだ。
仲良しが過ぎるという括りだけでは語りつくせない。身内という関係性すら軽く飛び越えた。ふたりはまるで、互いの呼気を吸いあっているような、それ以外に今日をつなぐ方法なんて知らないみたいな、安寧なのか依存なのか、そのどちらでもあって、そのどちらもまるで的外れだった。
「どうせ恭ちゃんだって、」
くどいほどくり返される茜ちゃんの口癖は、校庭の砂が立ち舞うように吹いては散り、目の届かない隅の隅、奥の奥まで知らぬうち入り込んで、迷惑はずっと後で露わになるのだった。
わたしの記憶にある恭一と茜ちゃんは、いつもおなじ押し問答をくり返していた。それも、茜ちゃんに限ってはひどく幼稚な物言いで、いっさいのわがままは彼の前でのみ演じられた。
「それならぼくは、番い目《つがいめ》にでもなろうか。ぼくが箍《たが》にさえなってしまえば、きみのその不安はすべてこのぼくが受けとめてしまえる」
わたしたちは、まだほんの幼いこどもであったはずだった。
恭一は中等部へ進級したばかりで、成長を見越して仕立てられた学ランの詰襟がコルセットよろしく彼の喉元を締めあげていた。それは少しでも猫背になれば、無理やり首輪に繋がれた飼い犬の引きずられていく散歩風景のようでもあり、よってつねに背筋は凛々しくあった。
それから、赤いランドセルだ。あれはまるで、子どもたちの成長を引き留める枷のような代物だった。わたしたち姉妹は、最短四年から平均十三年の初等部に揃って二桁ギリギリの年月在学した。だから、年齢の上ではひとつしか違わなかった茜ちゃんと恭一の距離は、ここで一気に引き離された。年齢なんて関係ない、からだの成長は知識と教養に比例して育つのだから、こころとか気持ちとかいった代物は、往々にして子ども時代に置いてきぼりにされる。
たった五年で進級していった恭一は特異な子どものひとりに数えられていた。大人と呼ばれる人間たちから一目置かれていただけでなく、多大なる期待と数え切れぬほどの可能性を約束された子どもだった。しかしながら、不特定多数の人類に貢献することすら可能であった将来有望な少年は、どこにでもいる凡庸なひとりの子どもにみずから飲み込まれた。故に、わたしたち姉妹は疎まれる存在となったのだった。
幼い子ども目から見ても、わたしの物心つく頃にはもう、茜ちゃんは恭一の虜だった。それはもう狂信的なまでに。すべてを委ね、依存しきっていた。このわたしが妹という最強の特権をどれだけ振りかざしても、茜ちゃんの恭一に対する思い入れは何もかもを凌駕した。
とはいえ、わたしも茜ちゃんと恭一のやり取りを逐一覗きみてきたわけじゃない。だからこれは、一個人の勝手な妄想にすぎないし、すべては抽象的に過ぎる。わたしは、恭一という人間をまるで知らないのだから。