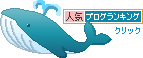わたしたちは子どものかたちをしていたけれど、いつのまにか精神ばかりが膨れあがった頭でっかちな子どもの群れに育っていた。
中等科・高等科はそれぞれ三年の一貫教育で、男女別の寮生活に変わる。初等科のあいだ、子どもたちは男女の区別なく育てられるが、恭一のように飛び抜けて進級していく子どもたちは、特別進学科に割り振られ、初等科へ通う子どもたちと引き続き生活だけは共にした。それは大人たちなりの配慮で、極めて人数の少ない特進科の生徒たちを子ども社会から逸脱させないためだった。
共同生活がもたらす優位性を、わたしたちの社会は近年最重要項目として教育方針の念頭に置いていた。知識や能力の格差は個々人の生まれ持った才能や、性格によってどうしても振れ幅が生じてしまう。一世紀ほど前には、子どもたちの能力差が浮き彫りなることに異様なまでの拒絶主義が蔓延し、ありとあらゆる順位、数値、点数制度がオブラートに包むことを至上命題とするような思想がまことしやかに社会を支配していたらしい。当時、子どもであった大人たちはゆとり世代と呼称され、彼らが作りあげたのがわたしたちの社会だった。
その後の悟り世代と呼ばれる大人たちが、現在の特進科をつくった。停滞した自立心の成長を、改めていかに育ててゆくか。そこで、子どもたちを盲目的に年齢で区分けることを廃止した。
世界は人間の生き方に呼応して変貌を遂げる。子どもたちは、それぞれの知識と教養に比例して育ち、各々が望んだからだの成長を手に入れるようになった。幼少期、まだ物心もつかないわたしたちは、ともに学び、食卓を囲む友人たちと足並み揃えて成長を重ねた。成長、すなわちそれは身体の変化であった。そして、学びとともにこころや気持ちといった代物には、徐々に変化の兆しがあらわれはじめた。
子どもたちの思考形態は、ゆとり・悟り世代の大人たちの想像をはるかに超え、大人びたという表現ではおよそ図ることのできない境地に達する生徒まで現れはじめた。
恭一の中等科への進級が確定したとき、わたしは十歳だった。瑠璃子は、進級を遅らせる手立てを企てなかったことについて、恭一をひどく責めたてた。子どもたちのなかには、自身の能力に気づいて、わざと留年を選ぶ者も少なくなかったのである。まだ確立しきっていない体制への不安が、水面下でそのような対処法を生み出す結果となっていた。なにより、カップリングの相手として目星をつけあった子どもたちほど、互いの進級について足並みそろえる風潮ができあがっていた。
「茜ちゃんを置いていく気なの、馬鹿なんじゃないの、それがどういうことかわかってんの、恭一は茜ちゃんを選んでたんじゃないの、ねえ、わたしが言ってることわかってる、ちゃんと聞いてる、放り投げる気なの、馬鹿なの、ねえ恭一、ふざけないでよ」
瑠璃子の怒り狂った様は、それまであくまで過程として、噂の範疇を出なかったわたしと恭一の関係性を、あたかも定められた運命のひとつに押し上げてしまうだけの強烈さがあった。
「だけど、方法はひとつじゃないと思うんだよ」
「先のことなんて、わたしたちにはわかんないよ、おつむのいい恭一にはわかるのかもね、だったら納得のいく説明をしてみせてよ、そんなあまちゃんななだめ方で、このわたしが引き下がるとでも本気で思ってんの、このまま茜ちゃんを置き去りになんかしたら、もう絶対に、一生許さない」
「瑠璃ちゃん、ぼくはまだここを出ていかない、中等科に進級するだけだよ、なにをそんなに心配しているんだ」
恭一はきっと、世界を変えるつもりでいたのだ。
わたしたちは子どものかたちをしていたけれど、いつのまにか精神ばかりが膨れあがった頭でっかちな子どもの群れに育っていた。ある意味、恭一は悟り世代の名残りのような子どもであった。数年後には、わたしたちにも適当な世代名がつくのかもしれない。
わたしは、恭一を好いていた。けれど、わたしは遅れ子だったから、人一倍遅れた子どもだったから、わからなかった。
瑠璃子は、わたしと一緒に進級した。あの子なら、もっと短い期間で進級できたはずなのに。わたしは平均以下だった。あの子は、わたしに合わせたのだ。恭一に迫ったやり方で、わざと。
わたしは、恭一の選択は正しかったと信じている。安易な行動は人生を棒にふる。流れに乗ることは、運命に逆らわないことと等しい。無論、瑠璃子には頭が上がらない。あの子のやさしさは常軌を逸している。わたしは彼女の執拗な愛情表現を体よくあしらいながら、手放すことなどできない。いつ、捨てられてしまってもおかしくないのに、あの子はわたしを手放さない。だからわたしは、せめて奢らない努力をする。わたしという人間のすべてを、あの子のために捧げられるように。
妙な夢を見たのだった、わたしたち姉妹は同時進級したというのに、夢のなかでは学年違いだと思い込んでいた。夢で見たような日々を、わたしは一日だって知らない。たった一年早く生まれただけで、姉と妹という、もはやあってないような関係性を求めたのかもしれない。飛んだお笑い草だ。わたしたちは神さまにお祈りを捧げる。あしたもよい日でありますように、と。
ひとくち吸ってしまった
でも
やっぱりむせた