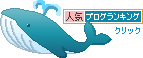木蓮は春のちょっと手前だから、少しさみしいね
「木蓮の花の純白ベルベットはウェディングドレスには向かないねー、せめて散るまではきれいでいたらいいのに、見てよ、まだ満開なのにもう茶色く荒んじゃって、灰かぶりのドレスだって、こんな中途半端な魔法の解け方はしないわよ」
定期健診に付き添った帰り道、まるでモミの木かと見まごうはだかの大きな三角の樹形が、てっぺんから幾百枚もの真っ白な花弁をまとっていた。教会の並びにまったく手入れのされていない木造の朽ちかけた空き家があって、植えっぱなしのツツジにボケ、去年の夏に生い茂って枯れたノウゼンカズラが無骨なソテツの葉先からぶら下がる。かろうじて敷地を囲っている板塀はどれだけの年月そこにあるのか、黒ずんでところどころささくれ、割れて、割れた隙間から猫の額ほどの庭を埋め尽くす雑草が、さらにここぞとあふれ出てくる。
家は周囲の晴れやかな陽気とは裏腹に、立ち入るものを全力で警戒し拒む用意が整っているとでも言わんばかりだ。広くない土地に、平屋建ての家屋がこじんまりとあったのかもしれない。しかし、人の住まなくなったわずかなこの空間は、いまや物言わぬ植物たちに占領され、今日という日は木蓮の樹が盛大に成長し、突如この世の春を呼び覚まさんと人の目に咲き誇っている。
「たぶん、きょねんも見たのに忘れてたわ。こんな、でっかかったっけ」
「うん、ちょっと拍子抜けするでかさだね」
よっこらせと効果音をつけたくなるような、両手を腰に当てて木蓮を見上げる瑠璃子の立ち姿は、いつのまに母の気配らしきものをまとったのか。
「あー満開絶好調のときに見たかったナア」
「きれいじゃない」
「だって、もっと完璧だったはずだもンー」
ミモザの花かんむり、クロッカスのブルーサファイア、スイートピーのパルファム、シロツメクサと四つ葉のエンゲージ。
「さむいさむい言って引きこもっていたのは、どこのどなたさんよ。もうちょっと歩きなさいって、さっき先生からも窘められていたじゃない」
「うーん、そうなるとやっぱり見にこれなかったかも」
木蓮は春のちょっと手前だから、少しさみしいね。
むかし、そんなことを言った大人がいた気がする。
「木蓮って、花が散ったらどんな木だったっけ」
「さア」
瑠璃子もわたしも、花が散ってしまったらこれが木蓮だったことどころか、ここに木蓮の木がそびえていたことにも、また気づかなくなってしまうのだから、思いだせない季節のかたちはことしも気付けないまま過ごしてしまうに違いないのだった。
「ひさかたの」
瑠璃子はわたしを置いて歩きはじめる。
「光のどけき春の日には、まだ早すぎるでしょ」
「うん、しかもそこまでいったら、みんなあっけなく散っちゃうね」
冬のコートに毛糸のマフラー。ポケットに手を入れて歩くのは危険ですよと手袋をすすめられ、瑠璃子は素直にその指示に従った。両手が空くようにリュックサックを背負い、足元は冬のはじめにわたしが送ったモヘアのぺたんこショートブーツを履いている。妹は、こんなにも素直な一面を併せ持っていたのかと、自分はロングコートのポケットに両手をつっこみ後ろをついて歩きながら感嘆すら覚える。この子はいま、その身に命を抱えているから、そうであることが当たり前なのだろうか。
茜ちゃんは僕のお嫁さんになりたいの。
小さくて幼かった。子どもの夢は取るに足らず、そこはかとなくつまらない。
「茜ちゃーん、きょうの検査、こないだみたいに血糖値ばーんって伸びちゃってなかったし、ごほうびデザート買って帰ろー、アイスアイス―」
わたしたちはもう、分厚い花びらの質感も、ほんの少し傷ついただけで茶色く変色してしまう傷みやすさもあっというまに忘れて、コンビニエンスストアの自動ドアを足踏みしてくぐり、あたたかな店内へと誘い込まれていった。